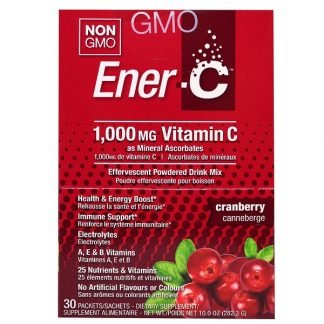━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「ピックアップ注目!!」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
マルチビタミン(207)
https://www.hfl8.com/product-category/%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%83%93%e3%82%bf%e3%83%9f%e3%83%b3/
マルチミネラルフォーミュラ(46)
https://www.hfl8.com/product-category/%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%83%9f%e3%83%8d%e3%83%a9%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%a9/
ビタミンPとは、かつてはフラボノイドと呼ばれる植物性化合物のグループを指す言葉でした。しかし実際には、これらの化合物はビタミンではありません。
フラボノイドにはいくつかの種類があり、果物、野菜、お茶、ココア、ワインなどに含まれており、特定の食品の色を構成したり、植物を紫外線や感染症から守る役目を持っています。また、健康上の利点もあると考えられています。
この記事では、ビタミンPの概要として、フラボノイドの種類、どんな食品に含まれるか、およびのどういう利点が考えられるかを説明します。
フラボノイドの種類とフラボノイドを含む食材
フラボノイドは、バイオフラボノイドとしても知られており、6つのサブクラスを持つポリフェノール植物化合物の1種です。現在知られている中でも、6,000以上のフラボノイドの存在が確認されています。
1930年に初めて科学者によってオレンジから抽出されたフラボノイドですが、この時は新しいタイプのビタミンであると考えられていたので、ビタミンPと名付けられました。
フラボノイドは植物に含まれており、植物を感染症から守るだけでなく、太陽や環境ストレスからの保護し、受粉のための昆虫の誘引などにも役立っています。また、ベリーやチェリー、トマトなど、多くの濃い色の果物や野菜の色も構成しています。
ここでは、フラボノイドのサブクラスとそれらを含む食材を紹介します。
- フラボノール:食材に含まれるフラボノイドの源となっているフラボノールには、カエンフェロール、ケルセチン、ミリセチン、フィセチンなどがあります。これらの化合物は、オリーブオイル、ベリー類、タマネギ、ケール、ブドウ、トマト、赤ワイン、お茶に含まれています。
- フラボン類:様々な食料源にみつかりますが、パセリ、タイム、ミント、セロリ、およびカモミールに含まれています。
- フラバノールおよびフラバン-3-オール:このサブクラスには、黒茶、緑茶、ウーロン茶に高濃度で含まれるエピカテキンやエピガロカテキンなどのカテキンが含まれています。フラバノールはまた、ココア、リンゴ、ブドウ、および赤ワインにも含まれています。
- フラバノン類:柑橘類の果物にみつかる、フラバノンは、オレンジ、レモン、および他の柑橘類の皮の苦味を構成します。フラバノンの例としては、ヘスペリチン、ナリンゲニン、およびエリオジ口オールが挙げられます。
- イソフラボン類:最もよく知られているイソフラボンは、ゲニスティンとダイジンであり、大豆や大豆製品に含まれています。
- アントシアニジン:ほとんどの赤、青、または紫色の果物や野菜にはアントシアニジンが含まれています。クランベリー、イチゴ、ブルーベリー、ブラックベリー、ぶどう、および赤ワインにはシアニジン、デルフィニジンやピオニジンといった化合物が含まれています。
まとめ
フラボノイドのサブクラスには、フラボノール、フラボン、フラバノール、フラバノン、イソフラボン、アントシアニジンがあります。様々なタイプのフラボノイドは、果物、野菜、赤ワイン、ココア、お茶などに豊富に含まれています。
健康上のメリット
フラボノイドには様々な健康効果があり、心臓病や糖尿病などの予防に役立つと考えられています。
最もよく研究されているフラボノイドの機能は、抗酸化物質としての働きです。抗酸化物質は、細胞の損傷や病気を引き起こす可能性のあるフリーラジカルと呼ばれる反応性分子の形成を減少させることが示されています。
非臨床実験 vs. 臨床実験
フラボノイドの効果についての研究は、ほとんどが非臨床実験で行われてきました。そのため、フラボノイドが体内でどういった効果を持つかは良くわかっていません。
実際、一般的にフラボノイドは吸収されづらく、体中に巡りわたる効率が悪いと言われています。
フラボノイドが体中に巡りわたる効率が悪いと言われる理由の一つには、代謝が大きく影響しているようです。そのため、フラボノイドは急速に体から排泄されることもあります。
フラボノイドが消費されると、代謝物と呼ばれる化合物に分解されます。これらの代謝物の中には、由来となったフラボノイドと類似した性質を示すものもあれば、そうでないものもあります。
さらに、フラボノイドが炭水化物、タンパク質、または脂肪と一緒に摂取されるかどうかが、体内吸収の効率に影響を与えることが研究から示唆されています。またこの吸収効率は腸内細菌の有無によっても影響を受けます。
よって、特定のフラボノイドが人の健康にどのような影響を与えるかの判断は難しいと言えます。
考えられる健康上の利点
十分ではないものの、いくつかの臨床実験からはフラボノイドに健康上の利点があることが示唆されています。
その多くは抗酸化作用に由来していますが、その他のメカニズムは完全には解明されていません。
- 脳の健康:いくつかの研究によると、ココア・フラバノールは、細胞の生存と記憶に関するシグナル伝達回路を介して、脳細胞を守り、脳の健康を高めることがあると示唆されています。
- 糖尿病:特定のフラボノイドの高い食事と2型糖尿病のリスク低減に関連性があることが、研究からわかっています。毎日300mgのフラボノイドを摂取するごとに、糖尿病のリスクは5%減少したということです。
- 心臓病:14の臨床試験からは、特定のクラスのフラボノイド、具体的にはフラボノール、アントシアニジン、プロアントシアニジン、フラボン、フラバノン、フラバン-3-オールの摂取が心臓病のリスクを大幅に低減させることが示唆されています。
これらの観察研究の結果から、フラボノイドが病気に抵抗する効果が示唆されていますが、実際フラボノイドが健康にどのように影響するかを完全に理解するには、さらなる研究が必要です。
この記事では、フラボノイドが健康にもたらすであろう効果のほんの一部を紹介しています。フラボノイドの機能や、フラボノイドの特定のクラスに関しては、研究が進んでいます。
まとめ
フラボノイドには様々な健康効果があると考えられていますが、それらのほとんどは、非臨床実験の結果から言われていることです。いくつかの人を対象とした観察研究の結果からは、フラボノイドが脳の健康を高め、心臓病や糖尿病のリスクを低下させる可能性があることが示唆されています。
用量とサプリメント
現在、フラボノイドは人の発育に不可欠なものではないと考えられているため、フラボノイドに推奨基準用量は定められていません。健康的な自然食品を豊富に含む食事は、必然的にフラボノイドを含み、健康にも良い効果をもたらします。
したがって、サプリメントは不要ですが、存在しないわけではありません。最も一般的なフラボノイドサプリメントには、ケルセチン、フラボノイド複合体、ルチンなどがあります。
フラボノイドサプリメントには標準化された用量がないため、商品ごとに異なる使用方法が記載されている場合がありますので、注意してください。また、これらのサプリメントによる副作用や潜在的な危険性は不明です。
専門家は、一般的に食べ物から自然に摂取されるフラボノイドの量には毒性のリスクはないが、高用量のサプリメントにはリスクがある可能性があると警告しています。
フラボノイドの高用量摂取は甲状腺機能に悪影響を及ぼし、服用している薬との相互作用や体内の他の栄養素のレベルに影響を与える可能性があります。
さらに、サプリメントは食品医薬品局(FDA)の規制が厳しくないため、ラベルに記載されている量とは異なるフラボノイドが含まれていたり、不純物が入っている可能性があります。
最後に、多くの研究からは、特定の栄養素を含む自然食品の方が、サプリメントよりも大きな効果が得られることが示されています。
サプリメントを試したい場合は、特に妊娠中や授乳中の場合、かかりつけの医師に必ず相談してください。
まとめ
フラボノイドは食品から広く摂取できますが、サプリメントも販売されています。しかし、これらのサプリメントは厳しく規制されておらず、知られていない害や副作用がある可能性があります。試す前には、必ず医師に相談するようにしましょう。
結論から言うと
かつてビタミンPとして知られていたフラボノイドは、色の濃い果物、野菜、ココア、紅茶、ワインなどに含まれる、非常に様々な種類を持つ植物性化合物です。
研究によると、フラボノイドは抗酸化物質として作用し、慢性疾患にかかりづらくする効果があるだろうと言われています。しかし、フラボノイドの人体への有益な効果は、代謝やその他の要因によって制限されている可能性があります。
フラボノイドの効果を最大限に引き出すためには、様々な植物性食品を食べるようにしましょう。サプリメントも販売されていますが、効果がよくわかっていないので、医師に相談してから摂取するようにしましょう。
サプリメントを摂取するよりも、フラボノイドを含む様々な食品を多く食べることを心がけたほうが、より健康に良いとも言われています。